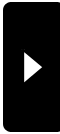2018年09月13日
意見するということ
文章を書くのは好きですが、読むのも好きで本はよく読んでます。
ネットでも色んな人のブログを読んだりしていて、そこから色々と感じることで楽しんでる部分はあります。
やはりその文章構成やボキャブラリから見えてくるのは書いてる人の人となりみたいなところ。
書いてる人の文章力から思想的なアプローチに至るまで、そこからその人自身の人間的レベルまでをもある意味推し量る指標になったりしていますね。
書いてる本人を知ってる場合なんかは特に。
だからといってそこにコメントしたりはしませんし、あくまで、自分の中で思って終わりにしてます。
僕の中だけであれこれと想像したり突っ込んだりって感じですね。
そういうところで独り楽しんでる。
コメントしたところで何もならないしね。
それはその人の考え方。
自分とは違う。
同じような思いの人もいたりしますが、それもまた心の中だけで同意。
色んなブログを見てると中にはその内容に対して(あれこれ物言いたくなるのもわからなくもないんだけど)長々と辛辣に突っ込んでるコメントなんかもあったりしますね。
でもね、思うんですよ。
意見してる側は覆面でしてるのなら、それは公平性を欠くのじゃないでしょうか?
フェアな状態でやりたいものです。

ネットでも色んな人のブログを読んだりしていて、そこから色々と感じることで楽しんでる部分はあります。
やはりその文章構成やボキャブラリから見えてくるのは書いてる人の人となりみたいなところ。
書いてる人の文章力から思想的なアプローチに至るまで、そこからその人自身の人間的レベルまでをもある意味推し量る指標になったりしていますね。
書いてる本人を知ってる場合なんかは特に。
だからといってそこにコメントしたりはしませんし、あくまで、自分の中で思って終わりにしてます。
僕の中だけであれこれと想像したり突っ込んだりって感じですね。
そういうところで独り楽しんでる。
コメントしたところで何もならないしね。
それはその人の考え方。
自分とは違う。
同じような思いの人もいたりしますが、それもまた心の中だけで同意。
色んなブログを見てると中にはその内容に対して(あれこれ物言いたくなるのもわからなくもないんだけど)長々と辛辣に突っ込んでるコメントなんかもあったりしますね。
でもね、思うんですよ。
意見してる側は覆面でしてるのなら、それは公平性を欠くのじゃないでしょうか?
フェアな状態でやりたいものです。

2018年09月12日
読めなくても音楽はできますが読めるにこしたことはない
音楽に取り組むのにおいて、それこそギターなら基本的な指使いをマスターしていくためのトレーニングが大事だって記しました。
でもそんな基本的なところで言えば、実は僕の場合、音楽を表現していく中でも一番基本中の基本である音符がパッと読めなかったりするんですね。
時間をかければ読めるには読めますが、でも目の前の楽譜の音符を見ながらパッパッパッと弾くなんてことは出来ないんです(^_^;)

あれ?読めないのって感じですが(苦笑)、そこの部分をマスターしないで今に至るんで、今は色んなものを表現したり形作るのを感覚でやってることが多いです。
ピアノをプレイするのにおいてやっぱり音符は読めたほうがいいかと思ったのと、ピアノプレイ技術を高めたいのもあって一時期京都までピアノを習いにも通ったりしてました。
音符の譜面でそれを課題にして色んな曲にも取り組みました。
でもね、結局は何度もやってるうちにフレーズを覚えちゃうから結局は音符を瞬時に読みながらプレイするところまで行きつかなかった。
で、ピアノもプレイは今もコード譜を見ながらやってます。
音符が書いてない譜面でなぜ弾けるのかとピアノを子供の頃から習ってこられた人に不思議がられたりしてましたけどね。
コード譜で鍵盤のキーやポジションがわかれば、あとはその曲のリズムやノリみたいなところに合わせて瞬時にアレンジしながらプレイする。
それが僕のスタイルなんです。
それはピアノに限らずギターは当然そうですし、僕の中で楽器をやっていくことはある種感覚的なところが大きいです。
なので、あまり決められたことをきっちりやっていくのは苦手で。
でもね、そういった感覚でやるとは言え、プレイフレーズは自分の中から引き出してこないといけない。
そのためにはたくさんの音楽を聴いて自分の引き出しの中に収めておかないといけないんです。
知らないモノを生み出せないから。
そんなところは中坊の頃から聴き倒した様々な洋楽の曲の数々が僕の中に息づいてるところはあります。
最近やりだした三線や三味線とかなんかもそういった感覚的なところでのアプローチなんですね。
何となくこういった感じで弾けばそれっぽくなるかというのがわかる。
そんなところを探しながら弦の上を指を動かしてる感じですね。
とは言いながらやっぱり基本は大事です。
音符は読めるにこしたことはない。
最近はドラムのレッスンとかでも音符譜面が出てくるので否が応でも読むことはやってます。
また、ギターでフレーズを伝えるのに音符を使って記したり。
少しづつですがモノするべく取り組んでます。
でもそんな基本的なところで言えば、実は僕の場合、音楽を表現していく中でも一番基本中の基本である音符がパッと読めなかったりするんですね。
時間をかければ読めるには読めますが、でも目の前の楽譜の音符を見ながらパッパッパッと弾くなんてことは出来ないんです(^_^;)

あれ?読めないのって感じですが(苦笑)、そこの部分をマスターしないで今に至るんで、今は色んなものを表現したり形作るのを感覚でやってることが多いです。
ピアノをプレイするのにおいてやっぱり音符は読めたほうがいいかと思ったのと、ピアノプレイ技術を高めたいのもあって一時期京都までピアノを習いにも通ったりしてました。
音符の譜面でそれを課題にして色んな曲にも取り組みました。
でもね、結局は何度もやってるうちにフレーズを覚えちゃうから結局は音符を瞬時に読みながらプレイするところまで行きつかなかった。
で、ピアノもプレイは今もコード譜を見ながらやってます。
音符が書いてない譜面でなぜ弾けるのかとピアノを子供の頃から習ってこられた人に不思議がられたりしてましたけどね。
コード譜で鍵盤のキーやポジションがわかれば、あとはその曲のリズムやノリみたいなところに合わせて瞬時にアレンジしながらプレイする。
それが僕のスタイルなんです。
それはピアノに限らずギターは当然そうですし、僕の中で楽器をやっていくことはある種感覚的なところが大きいです。
なので、あまり決められたことをきっちりやっていくのは苦手で。
でもね、そういった感覚でやるとは言え、プレイフレーズは自分の中から引き出してこないといけない。
そのためにはたくさんの音楽を聴いて自分の引き出しの中に収めておかないといけないんです。
知らないモノを生み出せないから。
そんなところは中坊の頃から聴き倒した様々な洋楽の曲の数々が僕の中に息づいてるところはあります。
最近やりだした三線や三味線とかなんかもそういった感覚的なところでのアプローチなんですね。
何となくこういった感じで弾けばそれっぽくなるかというのがわかる。
そんなところを探しながら弦の上を指を動かしてる感じですね。
とは言いながらやっぱり基本は大事です。
音符は読めるにこしたことはない。
最近はドラムのレッスンとかでも音符譜面が出てくるので否が応でも読むことはやってます。
また、ギターでフレーズを伝えるのに音符を使って記したり。
少しづつですがモノするべく取り組んでます。
2018年09月11日
ギターに取り組む
ここ最近ギターを習得するためのコツみたいなアプローチで記事を書いてます。
やはり僕にとって長年の夢だったギターを弾くことが出来るようになったことは僕の楽器ライフの中で大きなターニングポイントにもなりました。
出来ないと半ば諦めてもいただけに喜びはひとしおってとこなんですが、今の出来る喜びを得るのにはやはり結構な時間がかかってます。
そんな僕が味わってる喜びにビギナーの皆さんが少しでも早く到達してくれたらいいなという思いもありますし、僕がやってきて苦労したり悩んだりしてきたことも今となっては、そうやってやってきて今があるんだなって思うようなこともあります。
そんなところを記して、今ギターに取り組んでるけど苦戦したりわからなかったりしてる人が少しでも参考にしてもらえたらなんて思っています。
ギターをされてる皆さんの世代は幅広いですし、それぞれの世代で影響を受けたり、好きになったりしたサウンドも様々でしょう。
それこそ映像で見たバンドのギタリストがかっこよかった、自分もあんなギタリストのようにかっこいいフレーズやソロが弾けるようになりたい。
ということでそのバンドのバンドスコア譜を手にし、タブ譜に書かれてる指番号やポジション通りに押さえる練習をし繰り返してモノにする。
あるときにそんなアプローチでされてるビギナーの若い子に遭う機会もありました。
で、話してて、曲のキーは?だとかその部分のコードは?なんて質問をするとまったく何のこっちゃわからんみたいな感じだったので聞いてるとその子はひたすらそのかっこいい今時バンドのギタリストが弾いてるフレーズのみを練習してるそうで。
なのでたどたどしいながらもその曲のギターのバッキングは一応全編弾けてるんですね。
でもベースにあるところが理解出来てない。
ということは曲を増やす度にそういう練習をしていけばやりたい曲自体のバッキングは出来るようにはなってはいくのでしょうけど、応用が利かないなんてことになるんですね。
まぁ指使いの練習にはなるので役には立つには立つのですが。
でもね、それこそ例えばあるときに、ギターが出来ると周囲が認知してくれて、みんなで歌うから何某かの曲の伴奏をしてよなんて言われた時にパッと対応できないなんてこともあり得る。
歌詞とコードさえわかればストロークでジャカジャカ弾けばその時の周囲からのリクエストに応えられ、さらに人気者にもなり得るんです。
ところがやりたい曲のリフやフレーズの練習のみに終始してることで基本がわからないために他のかえって簡単だろうと思われる曲のはずなのに対応できないということになってしまうんですね。
バンドをやりたい。
好きな曲やバンドでの取り組む曲が決まってる。
自分はギター担当だ。
そんな状況だとやはり前述のような取り組み方になるんでしょうね。
う~ん、そういう状況だとそういったやり方にならざるを得ないのもわかります。
でもね、やっぱりギターに取り組むのなら、短期間で好きなバンドに到達するためのそんなエネルギーを基本的な段階を踏んだトレーニングをすることに費やして欲しいなと思うのです。
なかなか好きなバンドの曲に到達できないもどかしさはありますが、根気よくそんなやり方から徐々にレベルをあげていくアプローチでやっていけば、やがて好きなバンドのあの曲もこのギターフレーズも段々とちゃんと根底にあるところを理解しながらプレイできるようになっていくかと思います。
そしてそんな基本的なことを練習していけば、応用も利きますし、自身のスキルもあがっていきます。
まずは、ドレミを弾くところからスタート。
そして右手のアルペジオピッキングの練習。
簡単な曲をアルペジオプレイするところから地道にいやっていく。
唱歌や童謡なんかが最初に取り組むのには難易度も低くていいです。
そういった簡単な曲、短い曲等のコードプレイからですね。
でも、そんな曲が出来る数が増えていくだけで達成感は得られます。
そして段々曲の難易度をあげていき、アルペジオもストロークも色んな奏法があるのでモノにしていく。
簡単なソロフレーズに取り組んでみたりしていく。
そうやっていけばやがて色んなパターンのプレイが出来るようになっていきます。
うちの教室ではそんなアプローチで楽しくギターをモノにしていけます。
興味のあるかたはぜひ一度お越しくださいませ。

やはり僕にとって長年の夢だったギターを弾くことが出来るようになったことは僕の楽器ライフの中で大きなターニングポイントにもなりました。
出来ないと半ば諦めてもいただけに喜びはひとしおってとこなんですが、今の出来る喜びを得るのにはやはり結構な時間がかかってます。
そんな僕が味わってる喜びにビギナーの皆さんが少しでも早く到達してくれたらいいなという思いもありますし、僕がやってきて苦労したり悩んだりしてきたことも今となっては、そうやってやってきて今があるんだなって思うようなこともあります。
そんなところを記して、今ギターに取り組んでるけど苦戦したりわからなかったりしてる人が少しでも参考にしてもらえたらなんて思っています。
ギターをされてる皆さんの世代は幅広いですし、それぞれの世代で影響を受けたり、好きになったりしたサウンドも様々でしょう。
それこそ映像で見たバンドのギタリストがかっこよかった、自分もあんなギタリストのようにかっこいいフレーズやソロが弾けるようになりたい。
ということでそのバンドのバンドスコア譜を手にし、タブ譜に書かれてる指番号やポジション通りに押さえる練習をし繰り返してモノにする。
あるときにそんなアプローチでされてるビギナーの若い子に遭う機会もありました。
で、話してて、曲のキーは?だとかその部分のコードは?なんて質問をするとまったく何のこっちゃわからんみたいな感じだったので聞いてるとその子はひたすらそのかっこいい今時バンドのギタリストが弾いてるフレーズのみを練習してるそうで。
なのでたどたどしいながらもその曲のギターのバッキングは一応全編弾けてるんですね。
でもベースにあるところが理解出来てない。
ということは曲を増やす度にそういう練習をしていけばやりたい曲自体のバッキングは出来るようにはなってはいくのでしょうけど、応用が利かないなんてことになるんですね。
まぁ指使いの練習にはなるので役には立つには立つのですが。
でもね、それこそ例えばあるときに、ギターが出来ると周囲が認知してくれて、みんなで歌うから何某かの曲の伴奏をしてよなんて言われた時にパッと対応できないなんてこともあり得る。
歌詞とコードさえわかればストロークでジャカジャカ弾けばその時の周囲からのリクエストに応えられ、さらに人気者にもなり得るんです。
ところがやりたい曲のリフやフレーズの練習のみに終始してることで基本がわからないために他のかえって簡単だろうと思われる曲のはずなのに対応できないということになってしまうんですね。
バンドをやりたい。
好きな曲やバンドでの取り組む曲が決まってる。
自分はギター担当だ。
そんな状況だとやはり前述のような取り組み方になるんでしょうね。
う~ん、そういう状況だとそういったやり方にならざるを得ないのもわかります。
でもね、やっぱりギターに取り組むのなら、短期間で好きなバンドに到達するためのそんなエネルギーを基本的な段階を踏んだトレーニングをすることに費やして欲しいなと思うのです。
なかなか好きなバンドの曲に到達できないもどかしさはありますが、根気よくそんなやり方から徐々にレベルをあげていくアプローチでやっていけば、やがて好きなバンドのあの曲もこのギターフレーズも段々とちゃんと根底にあるところを理解しながらプレイできるようになっていくかと思います。
そしてそんな基本的なことを練習していけば、応用も利きますし、自身のスキルもあがっていきます。
まずは、ドレミを弾くところからスタート。
そして右手のアルペジオピッキングの練習。
簡単な曲をアルペジオプレイするところから地道にいやっていく。
唱歌や童謡なんかが最初に取り組むのには難易度も低くていいです。
そういった簡単な曲、短い曲等のコードプレイからですね。
でも、そんな曲が出来る数が増えていくだけで達成感は得られます。
そして段々曲の難易度をあげていき、アルペジオもストロークも色んな奏法があるのでモノにしていく。
簡単なソロフレーズに取り組んでみたりしていく。
そうやっていけばやがて色んなパターンのプレイが出来るようになっていきます。
うちの教室ではそんなアプローチで楽しくギターをモノにしていけます。
興味のあるかたはぜひ一度お越しくださいませ。

2018年09月10日
まずはアルペジオ
さて日々充実して過ごしてるおかげか時間が早く過ぎていきます。
1週間で考えてもすぐに週末がやってくる感覚がありますしね。
早や9月も半ばに差し掛かろうとしてます。
皆さん、やり残したことはありませんか?
今年の誓いだとかを立てたかた、もう秋です。
年末までに間に合いそうですか?(笑)
今度、今度と思っているうちにすぐに日が経ってしまって、できなかったなぁなんて思われてるかたもいらっしゃるんじゃないでしょうか。
最近加齢とともに体力の衰えを感じてますが、子供相手の仕事でもありますし、体力がモノをいうところもあったりしてそんな時に体力の衰えで自分でがっかりしてみたり(苦笑)。
子供たちと一緒に身体を動かしてみる。
あ、ブリッジができない、逆立ちができない・・・。
あ~あ・・・。
出来てたことが出来ない、すぐに息があがる、そんなところで加齢を感じます。
歳をとるほどに何かをやることに対して困難さが若い時に比べて増してるんですね。
そう、何かをやろう、あと何年かしたら、なんて目標というかおっしゃってるかたも見かけたりします。
多分ね、そういってるうちにできなくなる可能性が大なんですよ。
熱いうちに打て なんて格言もあるじゃないですか。
やっぱりね、思った時がやる時なんですよ。
ちょっと憧れがある、だとか、あんなの出来たらいいな、と思ったらすぐに動くべきですよ~
・
・
・
さて、ギターを独学でされるかたは、まずはコードを押さえてストロークでジャカジャーン!って感じで始められるかたも多いかと思います。
うちにレッスンに来られてるかたに話を聞いていても最初に独学でやって行き詰まり、うちでレッスンを受講頂くようになったかたがおられて、そのかたも聞いてるとストロークでやる以外に考えられなかったと言われてました。
そう、アルペジオでプレイするなんて自分には絶対に無理だと。
でもね、うちで受講頂いてからはアルペジオをまずは練習してもらうようにしました。
そしてやがて出来るようになられました。
今は本当に夢のようだとおっしゃってます。
そうなんです。
やっぱり最初はコードフォームを押さえることも大事なんですが、並行して右手のアルペジオプレイの練習もするといいんです。
コードフォームと一緒に何とかしようって思わなくてもいいです。
とりあえずアルペジオの練習は右手のピッキングを繰り返すことだけに特化して繰り返すんです。
左手は何も押さえないで。
とにかくアルペジオのピッキングの練習だけをやる。

何度も繰り返してるうちにピッキングのリズムが揃うようになります。
そうしてから初めて左手のコードフォームを何か押さえてください。
右手のピッキングができるようになってるのなら、例えばEだとかDだとかAmだとか、簡単なコードを押さえてアルペジオプレイをすればめっちゃ弾ける感を実感できるようになりますから。
そうするとね、ギターがちょっと楽しくなってくる。
アルペジオが出来ると、ビギナーのかたにとって喜びは格別で、めっちゃ出来るようになった感覚を味わえるんです。
ここ、大事。
まずはちょっとした達成感を得るアプローチですね。
そしてちょっと楽しくなってくると、もっとさらに頑張って練習しようと思えるようになりますから。
試てみてください。
1週間で考えてもすぐに週末がやってくる感覚がありますしね。
早や9月も半ばに差し掛かろうとしてます。
皆さん、やり残したことはありませんか?
今年の誓いだとかを立てたかた、もう秋です。
年末までに間に合いそうですか?(笑)
今度、今度と思っているうちにすぐに日が経ってしまって、できなかったなぁなんて思われてるかたもいらっしゃるんじゃないでしょうか。
最近加齢とともに体力の衰えを感じてますが、子供相手の仕事でもありますし、体力がモノをいうところもあったりしてそんな時に体力の衰えで自分でがっかりしてみたり(苦笑)。
子供たちと一緒に身体を動かしてみる。
あ、ブリッジができない、逆立ちができない・・・。
あ~あ・・・。
出来てたことが出来ない、すぐに息があがる、そんなところで加齢を感じます。
歳をとるほどに何かをやることに対して困難さが若い時に比べて増してるんですね。
そう、何かをやろう、あと何年かしたら、なんて目標というかおっしゃってるかたも見かけたりします。
多分ね、そういってるうちにできなくなる可能性が大なんですよ。
熱いうちに打て なんて格言もあるじゃないですか。
やっぱりね、思った時がやる時なんですよ。
ちょっと憧れがある、だとか、あんなの出来たらいいな、と思ったらすぐに動くべきですよ~
・
・
・
さて、ギターを独学でされるかたは、まずはコードを押さえてストロークでジャカジャーン!って感じで始められるかたも多いかと思います。
うちにレッスンに来られてるかたに話を聞いていても最初に独学でやって行き詰まり、うちでレッスンを受講頂くようになったかたがおられて、そのかたも聞いてるとストロークでやる以外に考えられなかったと言われてました。
そう、アルペジオでプレイするなんて自分には絶対に無理だと。
でもね、うちで受講頂いてからはアルペジオをまずは練習してもらうようにしました。
そしてやがて出来るようになられました。
今は本当に夢のようだとおっしゃってます。
そうなんです。
やっぱり最初はコードフォームを押さえることも大事なんですが、並行して右手のアルペジオプレイの練習もするといいんです。
コードフォームと一緒に何とかしようって思わなくてもいいです。
とりあえずアルペジオの練習は右手のピッキングを繰り返すことだけに特化して繰り返すんです。
左手は何も押さえないで。
とにかくアルペジオのピッキングの練習だけをやる。

何度も繰り返してるうちにピッキングのリズムが揃うようになります。
そうしてから初めて左手のコードフォームを何か押さえてください。
右手のピッキングができるようになってるのなら、例えばEだとかDだとかAmだとか、簡単なコードを押さえてアルペジオプレイをすればめっちゃ弾ける感を実感できるようになりますから。
そうするとね、ギターがちょっと楽しくなってくる。
アルペジオが出来ると、ビギナーのかたにとって喜びは格別で、めっちゃ出来るようになった感覚を味わえるんです。
ここ、大事。
まずはちょっとした達成感を得るアプローチですね。
そしてちょっと楽しくなってくると、もっとさらに頑張って練習しようと思えるようになりますから。
試てみてください。
2018年09月09日
音楽漬けの1日
日曜日なので仕事はお休み。
朝からはレッスンを1人済ませ、昼からはリハーサルです。
ネットで知り合ったボーカリストの男性でNさんといいます。
そこに僕の甥っ子のドラマのKを呼んでおき3人でセッションです。

プロの現場で音楽活動をされてたかたで、オリジナル曲もたくさんあって、それをステージでやりたいっていうことでメン募に投稿されてたのですが、そこに僕のほうからメッセージを送ったのですが、そこに返信頂いて色々とスケジュールの調整とかでメッセージのやりとりをし、1回目のリハが今日なのでした。
いや~、いいですね~。
オリジナル曲のクオリティも高くて。
ポップだし。
何よりもボーカリストとしての力量もハイレベルです。
カバー曲も交え、昼から3時間ほどをあれこれと喋りながらだらだらと進めました。
今日は初顔合わせでもあったし、とりあえずって感じでしたね。
お互いにセッションをしたことでその様子やアプローチとかもわかりましたし、これからぼちぼちと進めていこうって話に。
たちまちは来週の日曜昼間に多賀のほうでオープンマイクが企画されてて、そこに行くということでNさんとの活動がするする~っと始まります。
楽しみだ~
そして夜は17日にイベント出演が決まってるのでそのリハ。
またまた甥っ子のKと合わせます。
それは彼の地元の公民館に赴きました。
カバーやらオリジナルやらを6曲ほど。
振りつけの仕込みもあって、協力者もいてその振つけの指導も(笑)。
今日は1日、音楽漬けだったなぁ。
楽しかった。
ありがとう。
さて明日から仕事です。
朝からはレッスンを1人済ませ、昼からはリハーサルです。
ネットで知り合ったボーカリストの男性でNさんといいます。
そこに僕の甥っ子のドラマのKを呼んでおき3人でセッションです。

プロの現場で音楽活動をされてたかたで、オリジナル曲もたくさんあって、それをステージでやりたいっていうことでメン募に投稿されてたのですが、そこに僕のほうからメッセージを送ったのですが、そこに返信頂いて色々とスケジュールの調整とかでメッセージのやりとりをし、1回目のリハが今日なのでした。
いや~、いいですね~。
オリジナル曲のクオリティも高くて。
ポップだし。
何よりもボーカリストとしての力量もハイレベルです。
カバー曲も交え、昼から3時間ほどをあれこれと喋りながらだらだらと進めました。
今日は初顔合わせでもあったし、とりあえずって感じでしたね。
お互いにセッションをしたことでその様子やアプローチとかもわかりましたし、これからぼちぼちと進めていこうって話に。
たちまちは来週の日曜昼間に多賀のほうでオープンマイクが企画されてて、そこに行くということでNさんとの活動がするする~っと始まります。
楽しみだ~
そして夜は17日にイベント出演が決まってるのでそのリハ。
またまた甥っ子のKと合わせます。
それは彼の地元の公民館に赴きました。
カバーやらオリジナルやらを6曲ほど。
振りつけの仕込みもあって、協力者もいてその振つけの指導も(笑)。
今日は1日、音楽漬けだったなぁ。
楽しかった。
ありがとう。
さて明日から仕事です。
2018年09月08日
困った時の代理コード
ギターが面白いって記しました。
何を習熟するにおいてもそれなりの難易度はやはり必要なんだというのも実感させてくれる楽器なんです。
ちょっと取り組んだ程度では弾けるようになる楽器ではない。
最初にちょっと大きめな壁があり、そこで脱落していく人も多いのは、よくいうところのセーハコード(Fコード)の壁ですね。
Bmも同じく。
でもそんなところを越えて弾けるようになっていくと楽しくなってくる。
僕も最初の頃なんて出来る気がしませんでしたが、出来るようになってからはギターに対する思いが深くなっていきました。

うちのレッスンでビギナーの皆さんに伝えるのは押さえられなくて当たり前なんだからそこで悩まなくていいよっていうところです。
とは言いながら例えば某かの曲を課題にして進めるとそれらのセーハコードが出てくる場合もあります。
とりあえずは何度も練習してくださいとは伝えるのですが、どうしてもうまくいかないかたもいらっしゃいます。
いや、そんなかたでも何度も何度も繰り返してやればいつかは出来るようにはなるんですよ。
でもね、そのセーハコード以外のところはそこそこ出来てる人の場合なら、そんなセーハコードのところを違うコードに置き換えることでその曲をクリアすることも出来ますよね。
F は Dm7 に。
Bm は D に。
多少の違和感もありますが、構成音的に似てるコードなのでまったく間違ってるわけでもないんですね。
そうやってコードを置き換えることで、その人にとって停滞してた部分が前進出来るようになる。
それで何とかその曲の最後まで弾くことが出来るようになれば、達成感も得られるし、楽しくなってくるってわけです。
そしてそして何度もやっていくうちにコードも押さえられるようになります。
そうしてから F なり Bm なりをプレイするようにしてもいいんです。
FやBmができないといってそこに固執して最終的にやめようと思ってしまうくらいなら、代理で別のコードに置き換える方法もあるという話でした。
そんなことを教えてくれるのも教室のいいところですよね。
何を習熟するにおいてもそれなりの難易度はやはり必要なんだというのも実感させてくれる楽器なんです。
ちょっと取り組んだ程度では弾けるようになる楽器ではない。
最初にちょっと大きめな壁があり、そこで脱落していく人も多いのは、よくいうところのセーハコード(Fコード)の壁ですね。
Bmも同じく。
でもそんなところを越えて弾けるようになっていくと楽しくなってくる。
僕も最初の頃なんて出来る気がしませんでしたが、出来るようになってからはギターに対する思いが深くなっていきました。

うちのレッスンでビギナーの皆さんに伝えるのは押さえられなくて当たり前なんだからそこで悩まなくていいよっていうところです。
とは言いながら例えば某かの曲を課題にして進めるとそれらのセーハコードが出てくる場合もあります。
とりあえずは何度も練習してくださいとは伝えるのですが、どうしてもうまくいかないかたもいらっしゃいます。
いや、そんなかたでも何度も何度も繰り返してやればいつかは出来るようにはなるんですよ。
でもね、そのセーハコード以外のところはそこそこ出来てる人の場合なら、そんなセーハコードのところを違うコードに置き換えることでその曲をクリアすることも出来ますよね。
F は Dm7 に。
Bm は D に。
多少の違和感もありますが、構成音的に似てるコードなのでまったく間違ってるわけでもないんですね。
そうやってコードを置き換えることで、その人にとって停滞してた部分が前進出来るようになる。
それで何とかその曲の最後まで弾くことが出来るようになれば、達成感も得られるし、楽しくなってくるってわけです。
そしてそして何度もやっていくうちにコードも押さえられるようになります。
そうしてから F なり Bm なりをプレイするようにしてもいいんです。
FやBmができないといってそこに固執して最終的にやめようと思ってしまうくらいなら、代理で別のコードに置き換える方法もあるという話でした。
そんなことを教えてくれるのも教室のいいところですよね。
2018年09月07日
ギターの楽しさ
今まで楽器をやってきて、一番深くて面白いと思える楽器はギターです。
あ、僕にとってという話ですが。


僕の楽器歴は、ドラムから始まり、ピアノに取り組み、カホンやジャンベ等のパーカッションにも取り組み、あれこれとやりました。

その時に一時的にはそれぞれにはまったりしましたが、でもその熱が長続きしない。
その後ウクレレにいきます。
ギターは難しかったけど、ウクレレは僕でも何とかなった。
練習嫌いな僕にはほどよい難易度だった。
やっていくうちにそれなりに弾けるようになっていきました。
中坊の頃からギターに対する憧れが強く、当時アナログレコードで色んな洋楽アーティストを聴き漁りましたが、ギターソロだとかギターの歪んだ音がひとつの聴く時の基準になってたりしましたね。
ギターのサウンドがめっちゃ好き。
自分でも弾けたらいいのになぁ・・・。
で、取り組むんだけど、なんかモノにできない。
自分にはギターは無理なんだ。
そう僕の中で思い込むに至ります。
でもね、弦楽器を持ってステージに立つ自分の姿はどこか自分の中でイメージしていました。
できないのにね。
そんな夢が長くくすぶってました。
そしてウクレレとの出会い。
ギターが出来なかった僕が何とか弾けるようになっていった。
ウクレレを抱えてステージに上がれるようになった時の僕の喜びは格別なものがありました。
ギターではないけど、弦楽器を持って弾き語りしてる自分が誇らしげでさえありました。
ウクレレ弾き語りスタイルがしばらくの間僕の定番スタイルとして続きます。
その後お店をやるようになり、色々とあって必要にかられたのがきっかけとなり、ようやく重い腰をあげたのでした。
2012年頃からギターの練習に取り組み出します。
2013年のリリースした僕のCD音源は僕のプレイするギターのサウンド(アコギ)が収められてるので、そこらへんからが僕のギターキャリアのスタートになります。
今年でギターに取り組み出して6年になりますね。
6年やってきてようやくそれなりに弾けるようになってきたかなって感じなので、やはり僕が今まで取り組んできた楽器の中では一番時間がかかってます。
そして深い。
やるほどに面白さが自分の中で増していく。
最近になって長年の憧れだったスライドギターにも取り組みだし、まがりなりにもちょこっと弾けるようになってきました。
巷にいらっしゃるたくさんのギタリストの皆さんからすれば、まだまだ駆け出しの僕のギターではありますが、僕自身が本当に楽しんでるというか、心地がいいんですね。
そして最近はライブを中心とした音楽活動とは路線変更してるだけに、楽器を楽しむ余裕も出来てきてて自分的にも上達できるチャンスかと思ってます。
ここでグッと伸びたいです。
あ、僕にとってという話ですが。


僕の楽器歴は、ドラムから始まり、ピアノに取り組み、カホンやジャンベ等のパーカッションにも取り組み、あれこれとやりました。

その時に一時的にはそれぞれにはまったりしましたが、でもその熱が長続きしない。
その後ウクレレにいきます。
ギターは難しかったけど、ウクレレは僕でも何とかなった。
練習嫌いな僕にはほどよい難易度だった。
やっていくうちにそれなりに弾けるようになっていきました。
中坊の頃からギターに対する憧れが強く、当時アナログレコードで色んな洋楽アーティストを聴き漁りましたが、ギターソロだとかギターの歪んだ音がひとつの聴く時の基準になってたりしましたね。
ギターのサウンドがめっちゃ好き。
自分でも弾けたらいいのになぁ・・・。
で、取り組むんだけど、なんかモノにできない。
自分にはギターは無理なんだ。
そう僕の中で思い込むに至ります。
でもね、弦楽器を持ってステージに立つ自分の姿はどこか自分の中でイメージしていました。
できないのにね。
そんな夢が長くくすぶってました。
そしてウクレレとの出会い。
ギターが出来なかった僕が何とか弾けるようになっていった。
ウクレレを抱えてステージに上がれるようになった時の僕の喜びは格別なものがありました。
ギターではないけど、弦楽器を持って弾き語りしてる自分が誇らしげでさえありました。
ウクレレ弾き語りスタイルがしばらくの間僕の定番スタイルとして続きます。
その後お店をやるようになり、色々とあって必要にかられたのがきっかけとなり、ようやく重い腰をあげたのでした。
2012年頃からギターの練習に取り組み出します。
2013年のリリースした僕のCD音源は僕のプレイするギターのサウンド(アコギ)が収められてるので、そこらへんからが僕のギターキャリアのスタートになります。
今年でギターに取り組み出して6年になりますね。
6年やってきてようやくそれなりに弾けるようになってきたかなって感じなので、やはり僕が今まで取り組んできた楽器の中では一番時間がかかってます。
そして深い。
やるほどに面白さが自分の中で増していく。
最近になって長年の憧れだったスライドギターにも取り組みだし、まがりなりにもちょこっと弾けるようになってきました。
巷にいらっしゃるたくさんのギタリストの皆さんからすれば、まだまだ駆け出しの僕のギターではありますが、僕自身が本当に楽しんでるというか、心地がいいんですね。
そして最近はライブを中心とした音楽活動とは路線変更してるだけに、楽器を楽しむ余裕も出来てきてて自分的にも上達できるチャンスかと思ってます。
ここでグッと伸びたいです。
2018年09月06日
ダブルバージョン
今自宅にコロえもんが2つあります。
昨日はそれ2つを連動するようくっつけてみました。

ひとつのほうのゴールBOX部分から新たなレールを増設し、もう一方のほうのスタート部につなぐ。
最初のほうのやつは台の上(これまた段ボールで作った)にのっけてです。
で、転がしてみると連結部から転がって下のコロえもんにのっかり転がっていき、最終的にゴールへ。
うまくいく時と停滞する時とがあるのでつなぐ方向を調整してみたりして何度も試してました。
こうなってくると、もっとつなげていきたい衝動にかられますね。
でももう置く場所もないし、作ったとしてもせいぜいあと1個くらいかな…。
なんかね、最近の僕の趣味みたいになってコロえもん作りにはまってますが、前述のように場所をとるものでもあるだけに、今作っておいてる部屋は手狭になってきているところで検討の余地ありですね。
今はどちらかというと欲しい人があるのなら差し上げたいところなんですが、でもこれが欲しい人なんているのか…?(苦笑)
そう思うと自己満足だけのレベルってことになってその程度ではダメだとも思うし…。
今作ってるコロえもんの弱点は作って日が経つと、自重でレールが垂れ下がり、ボールが停滞してしまうパートが出てくること。
その都度なおしてはいますが、これがそうなっていかない造りを最初から施さないと思っています。
それとガムテープで貼りあわせていく造形がややもすると汚く感じる部分もあったりして、貼り付けかたを意識しながらやらないと補正したりする部分でガムテープがやたら重ね着みたいになってるところもあったり。
でもね、今はある意味試行錯誤段階かとも思ったりしています。
作っていく毎にそうやって課題も感じてるだけにより成熟させていけたら、クオリティもあがっていくだろうしね。
まぁ今は作ること自体を楽しんでるところもあるので、色々と思うこともありますが、作っては人にあげたり、はたまた壊したりしながら、やっていこうかとも思っています。
昨日はそれ2つを連動するようくっつけてみました。

ひとつのほうのゴールBOX部分から新たなレールを増設し、もう一方のほうのスタート部につなぐ。
最初のほうのやつは台の上(これまた段ボールで作った)にのっけてです。
で、転がしてみると連結部から転がって下のコロえもんにのっかり転がっていき、最終的にゴールへ。
うまくいく時と停滞する時とがあるのでつなぐ方向を調整してみたりして何度も試してました。
こうなってくると、もっとつなげていきたい衝動にかられますね。
でももう置く場所もないし、作ったとしてもせいぜいあと1個くらいかな…。
なんかね、最近の僕の趣味みたいになってコロえもん作りにはまってますが、前述のように場所をとるものでもあるだけに、今作っておいてる部屋は手狭になってきているところで検討の余地ありですね。
今はどちらかというと欲しい人があるのなら差し上げたいところなんですが、でもこれが欲しい人なんているのか…?(苦笑)
そう思うと自己満足だけのレベルってことになってその程度ではダメだとも思うし…。
今作ってるコロえもんの弱点は作って日が経つと、自重でレールが垂れ下がり、ボールが停滞してしまうパートが出てくること。
その都度なおしてはいますが、これがそうなっていかない造りを最初から施さないと思っています。
それとガムテープで貼りあわせていく造形がややもすると汚く感じる部分もあったりして、貼り付けかたを意識しながらやらないと補正したりする部分でガムテープがやたら重ね着みたいになってるところもあったり。
でもね、今はある意味試行錯誤段階かとも思ったりしています。
作っていく毎にそうやって課題も感じてるだけにより成熟させていけたら、クオリティもあがっていくだろうしね。
まぁ今は作ること自体を楽しんでるところもあるので、色々と思うこともありますが、作っては人にあげたり、はたまた壊したりしながら、やっていこうかとも思っています。
2018年09月05日
台風一過 ~ そして習うということ
昨日の台風はすごかったですね。
特に風が強くて、うちはガレージのところに置いてる物置ロッカーが倒れて凹んでしまい使い物にならなくなりました。
これは倒れてたのを起こしたもの。

まぁ被害はこの程度で済んでよかったです。
ひどいところもあちこちであったようでお見舞い申し上げます。
・
・
・
さてこのブログでも度々記してますが、楽器をプレイするにおいてはその練習の大事さは何においても一番のポイントになってます。
やはり練習しないことには上達しないですから。
この程度でいいやと思った時点で成長は止まってしまいますが、練習し続ければ上達はしていくので、もうこれで完璧なんてタイミングはありませんから、時間を見つけては出来ればそれよりさらに高度なことを目指して取り組むといいかと思います。
僕は教室もやってるのでビギナーの皆さんの様子はずっと見てます。
やはりそんな中で上達していかれる様は教える側としても嬉しいものですし、そんなところは本人にも伝えてます。
最初の頃なら全然出来なかったことも今なら普通に出来てしまうというのはビギナーの皆さんにおいては気付かずに普通にやられてる人も。
そんな時に「それって始めた頃に苦労してたやん」って伝えると「あ、そういえばそうだった」と、あらためて自身を見直されたりなんてこともあったりします。
毎日の積み重ねの大事さを思いますね。
逆にギターのレッスンなんかをやってると最初の頃は特に「先生、これが押さえられなくて私には才能がない」だとか「これは私には無理です」なんておっしゃるかたもおられたりします。
そんな時にいつも言うのは最初から出来る人はいませんって言葉。
まずは左手のコードフォームが出来ないという壁に皆さんぶち当たります。
でも考えてみてくださいよ。
日常の中にはない手の形を形成しないといけないのですから、そこは出来なくて当たり前なんです。
小さい頃から日常にいつもそういう手の形をしないと生活が出来ないなんて状態ならいざ知らず。
それこそ最初に皆さんが苦労するFコードのフォームなんて日常の中にはあり得ない手の形です。
だから出来なくて当然ですって伝えます。
出来ないから練習する。
でも簡単には出来ないので繰り返し繰り返し何度も同じことをやる。
そうするとそのうちに出来るようになりますから。
そんなことを伝えると出来ない自分を卑下したりしてる人も安堵されたりなんてこともあったりします。
教室のよさはそんなところにもありますね。
独学では壁に当たると乗り越えるのが困難な部分も、師事をあおぎ習うことですり抜けていけたりしますから。
独学でギターに取り組まれた人が「Fコードフォームが出来なくて挫折した」と自分の過去を言われたりするケースをよく見受けます。
そこはめげずに繰り返したらいつか出来るようになったはずなんですが、初心者がぶち当たった壁は、先の見えない大きな不安要素となり自分の中で自分には無理だと勝手に諦める方向にいっちゃってるケースなんです。
誰もその先がどうなっていくのか教えてくれる人がいないとその不安がどんどん広がっていきやめる選択をしてしまう。
もうあとどれくらいやればこうなるよ、だとかそれはこうしたらもう少しやりやすくなるよみたいなことを教えてもらえることは、人に習うことで得られる特権みたいなものです。
経費がかかるのはある意味大事なショートカット手段であるがゆえ。
お金をかけて困難をなるべく避けて進むのか、お金をかけないで自分の努力だけで乗り切るか。
でも強い精神力を持ち、大きな時間消費をものともしない人なら独学でいけるのでしょう。
挫折しやすい人はお金をかけることで前進しやすくなり挫折の確率を低く出来ます。
でもね、あらためて最近思うのは、やはり楽器を習熟するのは独学より習ったほうがいいってこと。
早く達成感を得られる。
そして不安感もかなり軽減できる。
その対価として経費が発生するのは致し方ないし、むしろ何かをモノにするのにそういった投資は惜しむべきではないと思っています。
僕もいまだにドラムは月1ですがレッスンを受けてますし、以前はピアノも習いにわざわざ京都まで行ってましたし。
これらのおかげで僕の器楽演奏技術は以前と比べて飛躍的によくなったとは思っています。
あ、あくまで前に比べてという話ではありますが。
でも一人でやってたのではここまで上達できてなかったであろうことは容易に想像がつきます。
何かをモノにするのに投資するのって本当に大事で必要なことだと思います。
惜しまずに投ずれば、きっと後年いい形になって自分に返ってきますから。
飛び込んでみましょうよ。
特に風が強くて、うちはガレージのところに置いてる物置ロッカーが倒れて凹んでしまい使い物にならなくなりました。
これは倒れてたのを起こしたもの。

まぁ被害はこの程度で済んでよかったです。
ひどいところもあちこちであったようでお見舞い申し上げます。
・
・
・
さてこのブログでも度々記してますが、楽器をプレイするにおいてはその練習の大事さは何においても一番のポイントになってます。
やはり練習しないことには上達しないですから。
この程度でいいやと思った時点で成長は止まってしまいますが、練習し続ければ上達はしていくので、もうこれで完璧なんてタイミングはありませんから、時間を見つけては出来ればそれよりさらに高度なことを目指して取り組むといいかと思います。
僕は教室もやってるのでビギナーの皆さんの様子はずっと見てます。
やはりそんな中で上達していかれる様は教える側としても嬉しいものですし、そんなところは本人にも伝えてます。
最初の頃なら全然出来なかったことも今なら普通に出来てしまうというのはビギナーの皆さんにおいては気付かずに普通にやられてる人も。
そんな時に「それって始めた頃に苦労してたやん」って伝えると「あ、そういえばそうだった」と、あらためて自身を見直されたりなんてこともあったりします。
毎日の積み重ねの大事さを思いますね。
逆にギターのレッスンなんかをやってると最初の頃は特に「先生、これが押さえられなくて私には才能がない」だとか「これは私には無理です」なんておっしゃるかたもおられたりします。
そんな時にいつも言うのは最初から出来る人はいませんって言葉。
まずは左手のコードフォームが出来ないという壁に皆さんぶち当たります。
でも考えてみてくださいよ。
日常の中にはない手の形を形成しないといけないのですから、そこは出来なくて当たり前なんです。
小さい頃から日常にいつもそういう手の形をしないと生活が出来ないなんて状態ならいざ知らず。
それこそ最初に皆さんが苦労するFコードのフォームなんて日常の中にはあり得ない手の形です。
だから出来なくて当然ですって伝えます。
出来ないから練習する。
でも簡単には出来ないので繰り返し繰り返し何度も同じことをやる。
そうするとそのうちに出来るようになりますから。
そんなことを伝えると出来ない自分を卑下したりしてる人も安堵されたりなんてこともあったりします。
教室のよさはそんなところにもありますね。
独学では壁に当たると乗り越えるのが困難な部分も、師事をあおぎ習うことですり抜けていけたりしますから。
独学でギターに取り組まれた人が「Fコードフォームが出来なくて挫折した」と自分の過去を言われたりするケースをよく見受けます。
そこはめげずに繰り返したらいつか出来るようになったはずなんですが、初心者がぶち当たった壁は、先の見えない大きな不安要素となり自分の中で自分には無理だと勝手に諦める方向にいっちゃってるケースなんです。
誰もその先がどうなっていくのか教えてくれる人がいないとその不安がどんどん広がっていきやめる選択をしてしまう。
もうあとどれくらいやればこうなるよ、だとかそれはこうしたらもう少しやりやすくなるよみたいなことを教えてもらえることは、人に習うことで得られる特権みたいなものです。
経費がかかるのはある意味大事なショートカット手段であるがゆえ。
お金をかけて困難をなるべく避けて進むのか、お金をかけないで自分の努力だけで乗り切るか。
でも強い精神力を持ち、大きな時間消費をものともしない人なら独学でいけるのでしょう。
挫折しやすい人はお金をかけることで前進しやすくなり挫折の確率を低く出来ます。
でもね、あらためて最近思うのは、やはり楽器を習熟するのは独学より習ったほうがいいってこと。
早く達成感を得られる。
そして不安感もかなり軽減できる。
その対価として経費が発生するのは致し方ないし、むしろ何かをモノにするのにそういった投資は惜しむべきではないと思っています。
僕もいまだにドラムは月1ですがレッスンを受けてますし、以前はピアノも習いにわざわざ京都まで行ってましたし。
これらのおかげで僕の器楽演奏技術は以前と比べて飛躍的によくなったとは思っています。
あ、あくまで前に比べてという話ではありますが。
でも一人でやってたのではここまで上達できてなかったであろうことは容易に想像がつきます。
何かをモノにするのに投資するのって本当に大事で必要なことだと思います。
惜しまずに投ずれば、きっと後年いい形になって自分に返ってきますから。
飛び込んでみましょうよ。
2018年09月04日
嫉妬心
他人を妬む気持ちというのは自己評価を得たい気持ちの裏返しみたいなところがありますよね。

自身の実力を顧みた時にあの人は自分より優れてる、だから妬ましい、なんて思考展開になる。
自分が上でいたい、みんなからすごいと思われたい、でもあの人はちょっと自分より上だ、妬ましい、って感じでしょうか。
いや、僕だってそういう気持ちはゼロじゃない。
やはり自分が出来ないことを他人がやってるのを見たり聞いたりすると、ちょっと悔しくてそういった気持ちが湧いてきたりします。
ただ問題なのは、その気持ちでその対象の人に攻撃したりすることですよね。
まぁよくありがちなんですが、音楽の現場でもそういった辛辣な言葉を人に投げ掛けたりするかたもいらっしゃるようで、そんな被害に合った人の話を聞いたりすることもあります。
そこまでいかなくとも陰で悪口を言い触らすケースもあったり。
妬ましい、だから相手を攻撃する、では自分の実力は上がらずに相手を潰すことだけに躍起になってるところで、その妬みスパイラルがずっと続くことになります。
妬ましい気持ちがあるのなら、じゃああの人に負けない自分の実力をあげようと努力するほうにエネルギーを注いだほうがいいのではないでしょうか。
嫉妬心はある意味自身の努力のエネルギー源になるので、ある種必要なところでもあります。
負けてる、だから努力をして負けないようにする。
ここは大事なポイントです。
僕は今までツワモノのアーティストのステージを幾度となく目の当たりにしてきてその都度うちひしがれてきました。
こんなすごい人がいるなら自分なんて・・・、みたいな思考展開で音楽をやめようとまで思ったことも。
でも好きなんでやめられはしないのですが。
僕の場合は自分の実力のなさを何度も味合わされ、凹みはしましたが、結果として努力する方向に今は動いてます。
すごい人に圧倒され、自信をなくした。
でも自分もそこまではいかなくとも例え少しでもそんな域に近づくよう頑張る。
この場合は妬みとかじゃないんだけど、でもね、ある意味嫉妬心みたいなものですよね。
自分にそういう実力がないから自分よりはるかに実力がある人が羨ましい。
嫉妬心。
そこをエネルギーに変えて頑張れば全然いいわけで、それのおかげで自分の実力も上がって強くなる。
嫉妬心を元に相手を攻撃するのが一番かっこ悪いですよね。
嫉妬心。
それはある意味諸刃の刃なのかもしれません。
でも、やっぱり攻撃するのじゃなく、自分の実力を上げることに努力をしたいものです。

自身の実力を顧みた時にあの人は自分より優れてる、だから妬ましい、なんて思考展開になる。
自分が上でいたい、みんなからすごいと思われたい、でもあの人はちょっと自分より上だ、妬ましい、って感じでしょうか。
いや、僕だってそういう気持ちはゼロじゃない。
やはり自分が出来ないことを他人がやってるのを見たり聞いたりすると、ちょっと悔しくてそういった気持ちが湧いてきたりします。
ただ問題なのは、その気持ちでその対象の人に攻撃したりすることですよね。
まぁよくありがちなんですが、音楽の現場でもそういった辛辣な言葉を人に投げ掛けたりするかたもいらっしゃるようで、そんな被害に合った人の話を聞いたりすることもあります。
そこまでいかなくとも陰で悪口を言い触らすケースもあったり。
妬ましい、だから相手を攻撃する、では自分の実力は上がらずに相手を潰すことだけに躍起になってるところで、その妬みスパイラルがずっと続くことになります。
妬ましい気持ちがあるのなら、じゃああの人に負けない自分の実力をあげようと努力するほうにエネルギーを注いだほうがいいのではないでしょうか。
嫉妬心はある意味自身の努力のエネルギー源になるので、ある種必要なところでもあります。
負けてる、だから努力をして負けないようにする。
ここは大事なポイントです。
僕は今までツワモノのアーティストのステージを幾度となく目の当たりにしてきてその都度うちひしがれてきました。
こんなすごい人がいるなら自分なんて・・・、みたいな思考展開で音楽をやめようとまで思ったことも。
でも好きなんでやめられはしないのですが。
僕の場合は自分の実力のなさを何度も味合わされ、凹みはしましたが、結果として努力する方向に今は動いてます。
すごい人に圧倒され、自信をなくした。
でも自分もそこまではいかなくとも例え少しでもそんな域に近づくよう頑張る。
この場合は妬みとかじゃないんだけど、でもね、ある意味嫉妬心みたいなものですよね。
自分にそういう実力がないから自分よりはるかに実力がある人が羨ましい。
嫉妬心。
そこをエネルギーに変えて頑張れば全然いいわけで、それのおかげで自分の実力も上がって強くなる。
嫉妬心を元に相手を攻撃するのが一番かっこ悪いですよね。
嫉妬心。
それはある意味諸刃の刃なのかもしれません。
でも、やっぱり攻撃するのじゃなく、自分の実力を上げることに努力をしたいものです。